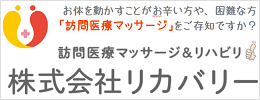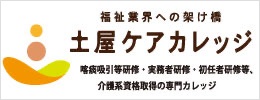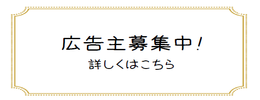第13回移動等円滑化評価会議報告~バリアフリー整備の現状と今後の課題~
2025年03月06日 バリアフリー

3月5日に移動等円滑化評価会議が開催されました。この会議は2018年のバリアフリー法改正で設けられた当事者評価の仕組みで、半年に一回開かれており、今回が13回目となります。
今回の議題は以下の通りです
- 移動等円滑化の進展状況について
- 第12回移動等円滑化評価会議における主なご意見と国土交通省等の対応状況
- 国土交通省等におけるバリアフリー関係の取り組み事例について
- その他
移動等円滑化の進展状況について
2025年度末の目標値と、2023年度末の現状値が報告されました。目標達成が難しい主なものは以下の通りです。
| 項目 | 現状 | 目標 |
|---|---|---|
| 視覚障害者誘導用ブロック(鉄軌道) | 45% | 100% |
| リフト付きバス(適用除外車両) | 約9% | 25% |
| 貸切バス | 1,229台 | 約2,100台 |
| 福祉タクシー※ | 52,553台 | 約90,000台 |
| 音響信号機及びエスコートゾーンの設置率 | 約56% | 100% |
| 移動等円滑化促進方針 | 44自治体 | 350自治体 |
| 移動等円滑化基本構想 | 325自治体 | 450自治体 |
※このうち、UDタクシーが25%以上の都道府県の割合は現状約9%(目標は各都道府県における総車両数の25%)
佐藤コメント
- 鉄道、旅客船、航空、道路、都市公園、路外駐車場、建築物は概ね目標値に近づいていますが、旅客船や航空、建築物は基準自体が不十分ですので、100%となっても全て使いやすいとはなりません。今後、基準の見直しが必要です。
- 鉄軌道においては視覚障害者誘導ブロックの敷設が進んでいません。
- リフト付きバスは、交通バリアフリー法ができた2000年時と比べてもほとんど増えておりません。空港アクセスバスは2021年から国内27空港の路線でバリアフリー車両の導入が始まりましたが、高速バスはほとんど導入されていません。
- UDタクシーのところはわかりにくいのですが、目標が各都道府県で25%なのですが、この25%を超えている都道府県の割合が9%というものです。実際の導入状況は、全国平均で23.5%(39,708台/168,836台)です。東京はオリパラに向けて集中的に導入したので65.2%と突出して多いのですが、全国平均を超える都道府県は東京、鳥取、愛知、千葉しかなく、10%未満が24県もあります。最下位の徳島は1.1%(10台/912台)です。
- 音響信号機も増えておりませんし、基本構想の策定も低調のままです。
主な意見
- ホームの段差と隙間の目標値入れていただいた。嵩上げ工事が終わっていても、目標数値に達していない場所が多い。そういうところの改善をしてほしい。
- 無人化される場合、基本構想で検討されることになっているはず。基本構想で無人化する場合どうするか。無人化できないようにする対策も必要。
- 地方空港のリムジンバスを調べたら、リフトの耐荷重が200kgだった。エレベーター式のもの、リフト式、両方200キロ。これでは電動車椅子によっては乗れないもの多い。最低300キロにしてほしい。
→(自動車局)対応を検討したい。
- UDタクシーは車に乗れるようになったが、移動中外が見れない問題がある。移動中の車窓を楽しめる視点が重要。開発時はそれも考えてほしい。
- 無人駅は、対策講じられるものはやってほしい。点字ブロック、音サイン等。また、地域住民の意見を聞く体制を必ず作って、対応してほしい。
- 道路は歩車分離式が増えて、視覚障害者は不安。車の音を頼りにできない。音響式やエスコートゾーンの設置が必要。音響式は近隣住民に配慮と言われるが、視覚障害者の命が危険に及ばされることはあってはならない。
- 大きなターミナル駅で移動の連続性が途切れている。人員不足で誘導ができない。視覚障害者にとっては誘導ここまでと言われても、動きようがない。移動の連続性が確保されるように、良い事例を参考に取り組んでほしい。
→(国交省)うまくいっている事例もあるので、調べてガイドラインに載せるなどしたい。
- ICTの開発には、最初の段階から視覚障害者も入れてほしい。後からではコストは上がる。さまざまな障害者が使う前提で、当事者の意見を聞いて開発してほしい。
→(国交省)開発段階から、検討していきたい。
- 観光や関連業界にもっと焦点が当てられることを期待している。バリアフリーのホテルの客室が不足していることや、観光バスの利用が難しいことが課題。これらの問題を解決することで、経済にも良い影響を与え、長期的にはコストを回収できるのではないか。
- みどりの窓口が機械に変わっている。聞こえないものには使いにくい。オペレーターが手話で会話できる方法の工夫もお願いたい。
- 駅ホーム、車両の中は音声情報の視覚化をお願いします。駅ではモニターが増えているが、もう少し具体的に内容が見られるように工夫して。事故が起こったときに耳が聞こえないものは何が起こったのかわからないので、わかるように工夫してほしい。
- リフト付きバス少ない。目標値を上げてほしい。
- 基本構想、マスタープランの目標達成が難しい状況。自治体の問題でもあり重要。策定をさらに進めてほしい。
- インバウンドで大きな荷物を運んでいる人が多い。場所を取り、邪魔で、高齢者、障害者が不便をしている。弊害あり。検討してほしい。
- 新幹線のWEB、JR東海もやってほしい。名古屋、新大阪利用者多い。エクスプレス予約で特急券は買えるが、乗車券は窓口のみ。
- UDタクシーの流しを手を上げて呼ぶと、車椅子だと止まってくれない。立っていると止まってくれる。実質的な乗車拒否。指導してほしい。
- 学校施設のバリアフリー化。体育館のステージに上がる方法が階段しかないところが多い。卒業式、ステージ発表等ステージに上がる機会がある。国からの補助も検討してほしい。
- 化学性過敏症の人は交通機関に乗れない。目に見えにくい障害。香害の実態把握に努めて。
DPIの意見
- 鉄道車椅子席・障害者割引乗車券のWEB予約を各社で導入してほしい
JR東のえきねっととても良い。WEBで車椅子席の予約をし、障害者割引の乗車券を購入できる。他の事業者は、WEBで申し込んでも、結局駅に行って発券しなければならない。各社どうなっているか状況を教えてほしい。
→(鉄道局)チケットレスはJR東えきねっとのみ。特急のWEB予約はJR東一部の特急で3/15から導入される(成田エクスプレスと、湘南)
- 駅の無人化をする前にバリアフリー整備をしてほしい。
都市部でも駅の無人化が始まっている。西武鉄道では、1日の利用者が2万4千人の鷹の台駅も無人化される。最低限の整備をしてからにしてほしい。段差と隙間の解消をして、単独乗降できるようにしてほしい。
西武鉄道が今年度から遠隔操作が導入された駅の近くに住んでいる車椅子ユーザーの話では、乗降介助を頼むために、毎回お客様センターに電話をして対応をお願いしているが、0570のナビダイヤルで、通話ごとに100円前後の費用がかかる。障害者だけに負担が発生しており、差別ではないか。西武鉄道に問い合わせると、改札付近にあるインターホン等でお知らせいただくことで対応可能というが、9時~17時のみで、早朝夜間や急に電車を利用するときは使えない。
- 既存車両のバリアフリー化を前倒しして実施してほしい
JR九州の特急ソニックは、車椅子席が非常に狭い。車椅子が通路にはみ出て、通る人が大変。車両の改修を前倒しして、新基準に対応したものしてほしい。
- 高速バスのリフト付き車両の導入促進
目標25%に対し、9%とほとんど増えていない。これは前回の第3次計画からずっと続いている問題。2000年の交通・バリアフリー法制定時はバリアフリー車両が開発されていなかったから、基準適用除外申請という仕組みが設けられ、申請すればバリアフリー化が免除されていた。しかし、今ではリフト式とエレベーター式が開発され、空港アクセスバスで導入されている。この課題を放置するのではなく、是非とも2025年度には、改善を取り組んでいただきたい。
- バス 次世代型電動車椅子の乗車拒否を改善してほしい
広島や名古屋では、一部の電動車椅子(次世代型電動車椅子)の乗車拒否がされている。差別解消法対応指針に固定できない車椅子は乗車を断って良いと書いており、これを根拠にハンドル型電動車椅子や次世代型電動車椅子の拒否が各地で起きている。このままほっておいてはいけない。改善のために何らかの対策に取り組んでほしい。
→(自動車局)対応を検討したい。
まとめ
今回も委員から多数の意見が出され、20分近く延長する活発な会議となりました。2023年度末のバリアフリー整備状況では、点字ブロック、バス、UDタクシー、基本構想などの進捗が低調なものも多く、新たな対策が必要です。
旅客船や航空は目標をクリアするものが多く、整備が進んでいるように見えますが、指標自体が不十分なものだったり、利便性という観点が考慮されていないため、100%達成されても利用しやすいとは言い難い状況です。これらの指標の見直しも必要となっています。さらに委員から指摘されたように、様々な課題があり、まだまだやるべきことは多いのです。
2026〜2030年のバリアフリー整備目標(第4次基本方針)は、現在「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」で議論されており、3月末の検討会で中間まとめが示され、夏には確定する予定です。誰もが自由に移動し、楽しめる社会を実現するために、今後も働きかけていきたいと思います。
報告:佐藤 聡(事務局長)