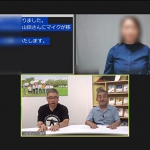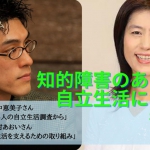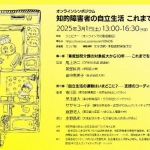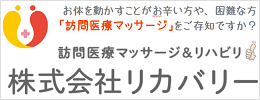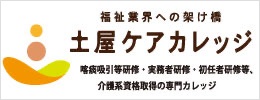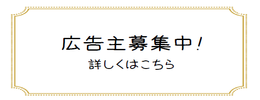スウェーデンの自立生活運動から学ぶ――ヘレナ・カルンストリームさん講演会レポート

4月11日(金)に東京都庁にて、ヘレナ・カルンストリームさんの講演会を開催いたしました。ヘレナさんはスウェーデンで1980年代から自立生活運動に取り組んできた障害当事者です。
当日は会場で約40人、オンラインで約60人の方がご参加くださりました。また、早坂義弘東京都議会議員、斉藤りえ東京都議会議員もご参加くださり、ご挨拶を頂戴しました。
ヘレナさんは、介助者との関係づくりや、スウェーデンでの障害者の生活の現状、運動の課題等等をお話しくださいました。私たち日本で運動する者にとって示唆に富んだお話だったと思います。
長旅でお疲れの中、長時間にわたってご講演いただいたヘレナさんに感謝申し上げるとともに、ご参加下さった皆様に心から御礼申し上げます。
△斉藤りえ東京都議会議員(右)
ヘレナさんの講演を聞いて
スウェーデンで自立生活運動を推進してきたヘレナさんの講演を聞き、日本の現状と重なる点が多いと感じました。特に、24時間介助が制度として整備された後、運動に関わる人が減ってきているという話は印象的でした。
一緒に闘える仲間が少ないと私自身も感じることがあり、今後どのように仲間を集っていくのか、考え続ける必要があると思いました。
日本でも、制度がある程度整ったように見えますが、介助者が不足していたり、駅の無人化や、新しい建物であってもバリアフリー化が不十分なことも多く、まだまだ当事者抜きで物事が決められてしまう現状も少なくないです。
私たちは、社会をよりよくするためだけでなく、現状を維持するためにも、声をあげ続ける必要があることを改めて感じました。
一方で、「日々を生きるだけで精一杯」「これ以上傷つきたくない」という思いがあることも想像にかたくないです。障害に対する考え方やスタンスは人それぞれであり、社会との関わり方も一様ではないはずだと思います。
また、運動自体を知らない当事者も多いでしょう。だからこそ、当事者同士がどのように関わり、それぞれの考えをどう社会に反映させていくかは、これからも向き合っていくべき課題だと感じました。
ヘレナさんが家族や介助者と丁寧に向き合いながら生活している様子も印象的でした。制度の整備だけでなく、人との関係性や日々のやりとりの積み重ねが重要であることを、改めて考えさせられました。
能松 七海(バリアフリー部会、CILふちゅう)