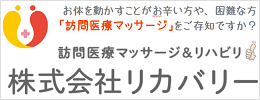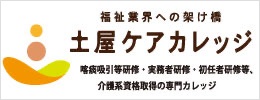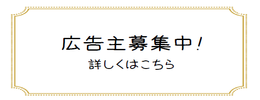4月23日文科省へ「障害差別の解消、インクルーシブ教育推進等」について要望を行いました

4月23日、インクルーシブ教育の実現や学校バリアフリーの推進など金城泰邦文部科学大臣政務官に要望書を手交してきました。
今回の要望は2025年度を期限として掲げたバリアフリー整備目標について、約3分の2の自治体が策定が未定という状況を踏まえた緊急性の高い学校バリアフリーの問題と優生裁判判決を踏まえた国の「行動計画」の実施と学習指導要領の改訂において、過去の優生教育をきちんと反省しインクルーシブ教育を推進すべきという点を中心に要望してきたものです。
要望書ではほかにも重要なことを要望しており、今後、交渉をすることととなっています。
今回は公明党福祉委員会委員長の三浦のぶひろ参議院議員のご尽力で実現しました。三浦議員にはご動向もしていただきました。いつも感謝です。DPIより尾上浩二副議長、西尾元秀常任委員、崔のほか、インクルーシブ教育事業の連携先である東京大学大学院バリアフリー研究開発センターのお二人も参加しました。
予定の時間よりかなりオーバーしてしまいましたが金城政務官には誠実にご対応いただき、心より感謝です。ご自分のご経験も踏まえながらお話もしてくださり、私たちの要望内容を踏まえて施策を進めてくださること、大いに期待しております。
崔 栄繁(議長補佐)
要望書全文は下記からご覧ください。
2025年4月23日
文部科学省大臣政務官
金城 泰邦 様
障害差別の解消、インクルーシブ教育推進等の要望
特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議
議長 平野みどり
貴省におかれましては、障害のある児童生徒の教育行政に、日々ご尽力のことと存じ上げます。
私たちDPI日本会議は、DPI(障害者インターナショナル)の国内組織として1986年に発足し、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現に向け取り組みを進める、全国89の加盟団体からなる障害当事者団体の連合体です。
2022年、国連障害者権利委員会による対日審査が行われ、同委員会から総括所見が出されました。私たちは結成当初から、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が、地域の同じ学校へ通い、ともに学ぶインクルーシブ教育の実現をめざして活動しており、総括所見の「勧告」は、めざす到達点が改めて示されたものと考えています。
この間地域の小中学校では、支援学級の在籍者が増えるとともに、不登校の児童生徒も増え続けています。その原因と考えられることとして、普通学級の状況が益々厳しくなってきている、「標準授業時間数・教育課程が多く、児童生徒も教師も余裕が無い」「常に過度の競争にさらされる」「1クラスの人数が多い」などがあるのではないでしょうか。
ともに学ぶ教育を実現するためには、障害者をはじめ支援が必要な児童生徒への環境整備・合理的配慮と同時に、すべての児童生徒が安心して楽しく過ごせる学校にすることが、まず求められます。
上記の認識の下、要望を以下に記します。
1. 障害者差別解消法関連
昨年4月から障害者差別解消法の改正法が施行されました。今年の春、私立高等学校が入学しないことを条件に受験を認めた事案については、既に貴省からも「障害を理由に具体的な検討を行わず受験や入学を拒むことは、不当な差別的取り扱いに該当し得ると考えられる」との見解が出されています。
今後このようなことが起きないよう、公立・私立の中学校・高等学校に対し「卒業後の適切な進路指導」「入学を前提とした就学相談」を行うよう、具体的な方策をご検討ください。その一環として、障害者差別解消法の対応要領、対応指針を改訂してください。
2.学校バリアフリーについて
本件に関しては貴省のご尽力に心から感謝しています。しかし、2025年度を期限として掲げたバリアフリー整備目標を達成できる自治体は240に止まり、現状のままでは校舎で11年以上、屋内運動場で20年弱かかると見込まれています。
問題なのは、国が掲げた整備目標の意味を理解していない自治体が多数を占めることです。約2/3の自治体が整備計画の策定が未定であり、単独事業としてバリアフリー化を行う意向のあるところはわずか2割弱に止まっています。
特に、「要配慮児童生徒の垂直移動の基礎となるエレベーター」は、その子にとっては毎日の学校生活に関わる切実な課題です。計画を組み替えて対応をして頂いている自治体は一部にありますが、多くは「建替時などに併せてエレベーター設置する」といった一般論での対応がなされ、「要配慮児童生徒等が在籍する学校のエレベーター設置が国の目標に掲げられていることを説明しても無視される」といった、本人・保護者からの悲痛な声が私たちのところには寄せられています。そして、バリアフリー法に定める昇降機には該当しない「キャタピラ式昇降機」で対応しようとする学校が未だに多く、子どもの尊厳と学習権の侵害にもなり得る事態が生じています。これらの点をふまえて、以下の点を力強く進めてください。
① 一日も早い目標達成のために、「要配慮児童生徒等在籍校のエレベーター設置」をはじめとしたバリアフリー整備計画が全ての自治体で策定されるよう、その義務化とともに、推進方策を示してください。
② 児童・生徒の入学予定を把握し、一日も早く当該学校のバリアフリー化を実現して安心して学べる環境を整備できるようにしてください。
③ さらに、各階へのバリアフリートイレの設置や体育館ステージへの昇降など、障害当事者の視点に立ったきめ細かな整備が進むよう指針の改訂並びに補助金の充実、障害当事者参画による設計や評価が進むような方策を示してください。
3.旧優生保護法並びに学習指導要領関連
昨年12月に旧優生保護法の強制不妊手術に対する最高裁の違憲判決を受け、政府は「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」を策定しました。障害者に対する許しがたい人権侵害に対し、早期の権利回復を行うためには、考え得る最大の対応策が必要です。現在、学習指導要領の改訂に向け準備が進んでいますが、その中で「優生保護法の被害・歴史についての学習を必修化する」改訂を求めます。
同時に、現在の学習指導要領は、標準授業時間数・学習内容が非常に多く、様々なひずみを生む原因の1つにもなっていると考えられます。障害のある児童生徒を含むすべての児童生徒が、安心して学校生活を過ごせるよう、余裕のある授業時間数・学習内容への改善を求めます。
4.「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行令」(以下、特例法施行令)第2条を見直して、大学の「介護等体験」で障害当事者が障害者の自立した生活を支援する自立生活センターでも実習が可能となるようにしてください。
現行の制度では社会福祉・医療関係・教育などの大学で、(単位認定はされませんが)全学部学生が対象となる「介護体験等」カリキュラムで、特例法施行令2条によれば「社会福祉施設等」とは「入所施設」などを指し、多くの自立生活センターは含まれません。これでは学生が、必要な支援を受けながら日常生活・社会生活を送る障害者の姿を知ることができません。また、東京都などでは学校や学生本人が実習先を選択できない仕組みとなっております。この点についても改善をお願いいたします。
5.以下の諸課題等について、ご検討お願いいたします。
① 障害者権利委員会の勧告の実施について
2022年10月に出された、障害者権利条約対日審査の「勧告」を踏まえた障害者権利条約(24条等)の国内実施の推進を強くお願いします。例えば、2022年4月に発出された「文科省通知」については、貴省とも意見交換をさせて頂きましたが、国連の総括所見でも撤回の要請が出ています。通常学級への就学希望者が特別支援学級在籍を勧められ、学ぶ時間数についても規定されるという状況は、ともに学ぶ教育を進めている方向性とは考えられません。可能な限り一緒の場で学ぶ実践に悪影響を与えないよう、ご検討をお願いします。
② 公立高校の定員内不合格について
昨年6月「高等学校入学者選抜等における配慮等について」(通知)が出され、「学ぶ意欲を有する生徒に対して、学びの場が確保されることは重要」「定員内でありながら不合格を出す場合には、・・・その理由が丁寧に説明されることが適切です」等示されたことは、大きな前進であると考えます。高校の授業料無償化が検討される中、高校での学びを希望するすべての障害者が、高校に進学できるよう、より具体的な方策をご検討ください。
③ 継続的な意見交換の場
今後とも、日本におけるインクルーシブ教育推進の課題に関して、継続的に話し合いの場を持っていただくようお願いします。
こんな記事も読まれています
現在位置:ホーム > 新着情報 > 4月23日文科省へ「障害差別の解消、インクルーシブ教育推進等」について要望を行いました