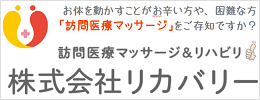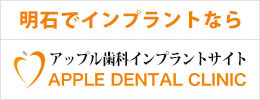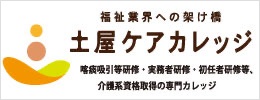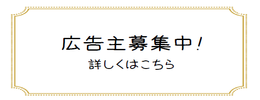【JICAビデオ教材紹介】インクルーシブな社会を目指して〜障害者運動から見た日本の物理的バリアフリーと街づくり〜
2025年03月25日 バリアフリー権利擁護国際/海外活動障害者権利条約の完全実施
JICAが日本の障害者運動と街づくりに関するビデオを作成しました。
本ドキュメンタリー動画は、日本における障害者運動の歴史をたどりながら、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指してきた人々の声と歩みを紹介しています。障害者権利条約やSDGsの理念を背景に、バリアフリーの街づくりの重要性が語られ、当事者による実体験と社会変革のプロセスが丁寧に記録されています。
この動画は、障害者が声を上げ、街に出て、制度を変え、社会を変えてきた実例を通じて、「共生社会」の実現とは何かを問いかけています。DPI日本会議から尾上、佐藤、DPI加盟団体のあいえるの会の白石さん、橋本さん、STEPえどがわの工藤さんも出演しています。是非ご覧ください。
●英語版(English Version) ●スペイン語版(Spanish Version)
ビデオの内容
00:00 第1章 障害者権利条約とSDGs「誰ひとり取り残さない」社会
01:34 第2章 日本の障害者運動の歴史
15:02 第3章 障害者運動の結果として得られた好事例 オリンピック・パラリンピックを背景とした当事者参画によるインクルージョンの進化
26:00 第4章 終わりに 国際協力における計画段階からの当事者参画の重要性
各章の内容
■ 第1章:障害者権利条約とSDGs
2006年に国連で採択された「障害者権利条約」が、日本でも2014年に効力を持ち、障害のある人々の権利を保障する国際的枠組みが整いました。しかし、かつての日本には制度的な保障が乏しく、多くの障害者が社会から隔離された生活を強いられていました。
■ 第2章:日本の障害者運動の歴史
戦後すぐに設けられた障害者福祉法のもと、施設中心の「全国コロニー構想」が進められ、障害者は社会から切り離される存在とされていました。これに異を唱えた人々が、自立生活を求めて街へと出ていく「自立生活運動」を展開。
特に「青い芝の会」やドキュメンタリー映画『さようならCP』の活動が社会に大きな衝撃と議論を巻き起こしました。
■ 第3章:交通バリアフリーの実現
1978年、川崎市で車椅子利用者のバス乗車拒否事件をきっかけに、交通機関におけるバリアフリーの必要性が広く認識されるようになりました。
その後、全国で「交通アクセス全国行動」などの運動が展開され、2000年には「交通バリアフリー法」が制定。駅のエレベーター設置やバリアフリートイレ、視覚障害者向けの点字ブロック整備など、都市部を中心に急速な改善が進みました。
■ 第4章:インクルーシブな社会に向けて
東京2020オリンピック・パラリンピックを契機に、バリアフリー基準の質的向上が求められ、新国立競技場や新幹線のユニバーサルデザインが当事者参画のもとで実現しました。
また、国際協力の分野でも、バングラデシュのダッカメトロ6号線など、日本の技術と障害当事者の知見を生かしたバリアフリー化が進められています。
以上
こんな記事も読まれています
現在位置:ホーム > 新着情報 > 【JICAビデオ教材紹介】インクルーシブな社会を目指して〜障害者運動から見た日本の物理的バリアフリーと街づくり〜